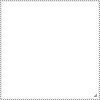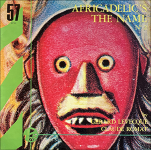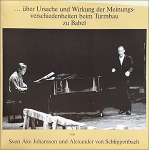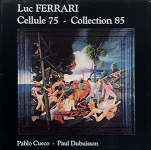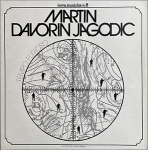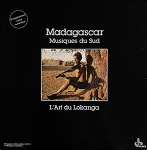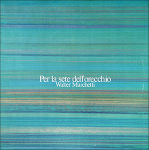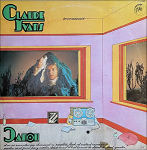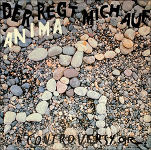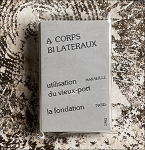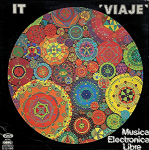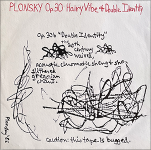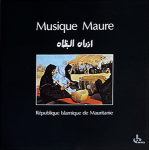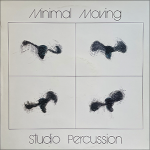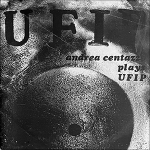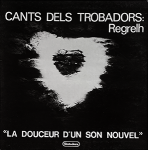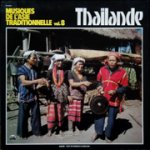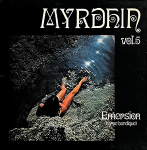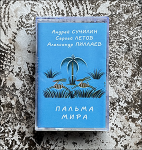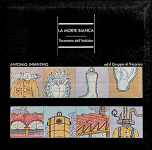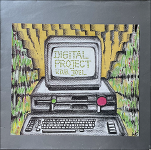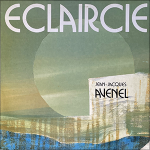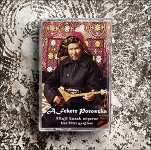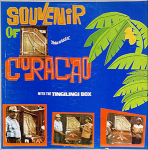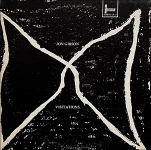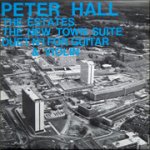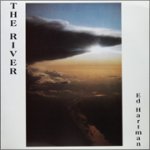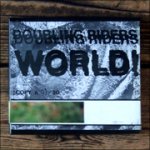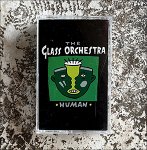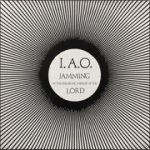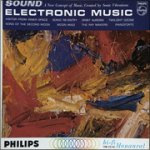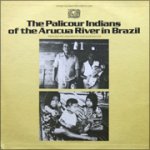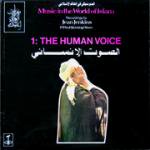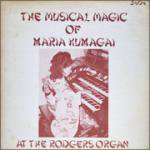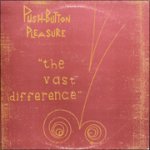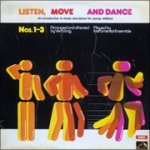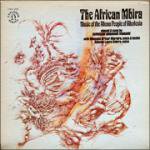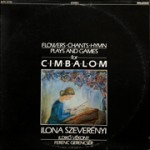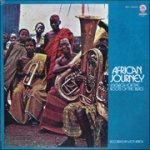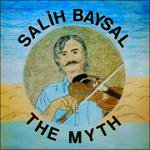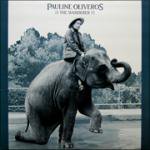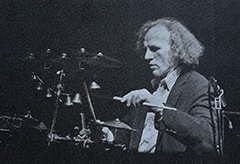| NEW ARRIVAL 送料改訂のお知らせ |
60年代英国ブルースから出発して、フラメンコギターの巨匠Manitas De Plataに師事、Keith Roweばりのプリペアドギター奏法と、古典/現代を横断する独自の即興方法論で... |
ジャズのマレットプレーヤーとしてキャリアをスタートさせ、80年代にAnthony Braxtonのジャズオーケストラに参加、その後も舞台や映画の為の作曲活動を続けている打楽器奏者/作曲... |
A.T.R.O.Xの首謀者Francesco PaladinoとPier Luigi Andreoniによって結成されたThe Doubling Riders。この作品から、超大陸音楽集団AktualaのWalter Maioliとの伝説グループ... |
Music Gallery Editionsを拠点とするトロントのインターメディアアートシーンから現れた、その名の通り大小かたちも様々な手製ガラス音具のみを操り、即興、ミニマリズム... |
80年代から90年代にかけて活動したベルリン発のグループI.A.O.。中心メンバーのAchim Kohlbergerが先導するベルリンテクノ勃興の動きとパラレルに制作された最充実期の... |
電子音響テクノロジーからマルチメディアに接続された総合芸術を生み出す作曲家Dick Raaymakers(aka Kid Baltan)と、ジャズと電子音楽を結ぶ実験に取り組んだTom Disseve... |
終息したかに見えたNYのフリージャズに、青白く燃え上がる鬼火のような冷たい炎を灯したロフトジャズムーヴメントを象徴するグループ、The Revolutionary Ensemble... |
疫病、他民族との抗争、強制労働などが原因で17世紀には絶滅してしまったという、かつて南米からカリブ海にかけて広く分布したアラワク族。アマゾン川流域の小さな村落で古来の... |
イスラム教の伝搬に伴って世界各地に分散し、ご当地の風土と混じり合って様々に変化ていった各地のイスラム音楽の痕跡を、『楽器』という共通言語を手掛かりに辿る全6編に及んだ... |
ボタンだらけの電子オルガンに着物姿のアジア女性というモンドな構図だけでも惹かれるもんがありますが、内容のほうも素晴らしい年代不詳(恐らく60年代)のレコード。アメリカで... |
Chrysanthemums、Jung Analysts、Yukio Yungといった宅録ポップバンドを立ち上げ、ポストパンク以上インディポップ未満の宙ぶらりんなシーンで活躍した端境の住人Terry Burrow... |
Vera Gray監修による、子供の耳と体の発育を促す62年の体操音楽シリーズ『Listen, Move and Dance』。ジャケがすごくいい感じのイラストに差し替わってる大変珍しい豪流通版... |
病気の治療にも使われたというアフリカ西南ジンバブエのショナ族に伝わる親指ピアノ『ムビラ』 |
ハンガリー伝統の打弦楽器ツィンバロムの響きを堪能できる名盤。60年代にかけてブダペストのリスト・フェレンツ音楽院で学び、作曲家・演奏家として伝統と現代を結ぶ優れ... |
のちに無数のオープンリールテープデッキを媒体とするグループThe Loop Orchestraを結成するRichard Fieldingらによってシドニーで結成され、手製のジャンク回路から生成さ... |
ブルースの名盤を数多く残した米Vanguardレーベルが、そのルーツを求めて西アフリカ諸国の民族音楽を録り歩いた67年の二枚組レコード。グリオたちの音楽から見えてくるブ... |
Rimarimba、C.W. Vrtacek、R. Stevie Mooreなどなど、当店でもお馴染みの端境の住人たちの憩いの場となっていた地下レーベルCordelia Recordsの一枚。レーベルオーナーで... |
極めて越境的な感性を持つ三人のトルコ人によって結成され、薫り立つようなエキゾチシズムとジャズインプロヴィゼイションとが鮮やかに交差する名作を生み出したSveda。その作品... |
巨大な貯水槽や洞窟といった特殊な共鳴環境で行われるコンサートをはじめ、『ディープ・リスニング』や『ソニック・メディテーション』といった、自然哲理と音楽を結びつける... |
フトゥリズモのお国で興った先鋭的なアートパンクショックの震源地のひとつであるボローニャから登場したThe Stupid Set。同地の看板グループであるGaznevadaから派生... |